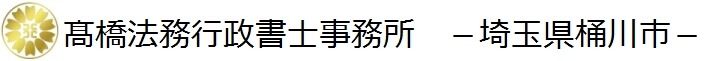遺言書・遺言公正証書・遺言書の証人

アットホームな雰囲気の行政書士事務所です。
迅速、親切丁寧に対応いたします。
ご挨拶
遺言書に関するご相談は、経験と知識が豊富な当行政書士事務所へ。
当行政書士事務所は、ご相談しやすい雰囲気づくりを心がけ、親身になってお客様のサポートをいたします。
対応エリアは、埼玉県内全域(桶川市、上尾市、北本市、鴻巣市、さいたま市、久喜市、伊奈町など)、その他全国対応いたします。
お気軽にお問い合わせください。
ご相談内容
・遺言書を書きたいが、どうすればよいかわからない
・遺言書を公正証書にしたい
・自分の財産は決して多くないが、将来、遺産相続でもめそう
・亡くなった親族が書いた遺言書が見つかった
・自筆証書遺言を書いたが、遺言書の保管や管理が不安
・相続人が一人もいないため、自分の財産をどうしたらよいかわからない
・相続人は配偶者のみで、遺言書をどのように書いたらよいかわからない
・相続人の中に行方不明者がいる
業務内容
遺言書の作成・相談
遺言公正証書の作成・相談
遺言書の保管・管理
遺言公正証書の証人(※1)
(※1)遺言書を公正証書にする場合、2人の証人が必要となります。
遺言書の種類
遺言書の作成方法には、以下のような種類があります。各方法には、長所/短所がありますので、状況に合わせ、作成されることをお勧めします。
自筆証書遺言
遺言者が全文を自筆します。遺言内容、年月日、氏名を記入し、押印(認印でも構いません)するだけです。
ただし、相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合、その目録についてはパソコンで作成したり、目録のみであれば他人が作成しても構いません。また不動産については登記事項証明書、預貯金については通帳のコピーを添付することもできます。ただし、目録の各ページに遺言者が署名押印する必要があります。
長所は、費用がかからず、簡便に作成できる点にあります。
短所は、記載内容が法律上有効であるかどうかわからないこと、遺言者の死後、遺言書が有効に作成されたかどうか(遺言者の自筆であるかどうか、作成時に意思能力があったかどうか、遺言者の意思で書かれたものか、など)が争われる可能性があること、遺言書の紛失の心配があること、家庭裁判所での検認手続きが必要となり、相続人全員に遺言書の内容が知られてしまうこと、が挙げられます。
公正証書遺言
公証役場において遺言書を作成します。
長所は、遺言内容を公証人が確認し、原本が公証役場に保管されるため、遺言内容に不備がないこと、遺言書の紛失の心配がないこと、遺言内容を他の相続人に知られる恐れがないこと、が挙げられます。
短所は、作成費用がかかる点です。
秘密証書遺言
あらかじめ遺言書を作成しておき、公証役場では、遺言書を作成したことの確認と遺言書の保管のみを行ないます。公証人は、遺言内容の確認を行ないません。
長所は、遺言内容を公証人や証人に知られないこと、遺言書の紛失の心配がないこと、が挙げられます。
短所は、記載内容が法律上有効であるかどうかわからないこと、作成費用がかかること、が挙げられます。
法務局での自筆証書遺言保管制度
法務局にて自筆証書を保管する制度です。
決められた形式で自筆の遺言書を作成し、申請書、本籍地と筆頭者の記載のある住民票、本人確認書類、手数料(3,900円)とともに、遺言者の住所地又は本籍地若しくは不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局に、遺言者本人が出向いて作成します。
長所は、家庭裁判所での検認が不要なこと、遺言者が亡くなった後に、相続人の一人が法務局に遺言書情報証明書の交付請求や遺言書又は遺言書保管ファイルの記録を閲覧したときは、他の相続人等に遺言書を保管している旨の通知がされること、遺言者が亡くなった後に、法務局から遺言者が指定する者に対し、遺言書を保管している旨の通知をすることができること、が挙げられます。
短所は、遺言者が法務局に出向く必要があること、他の相続人に遺言書の存在が知られてしまうこと、遺言書に記載された遺言執行者が遺言執行する場合に遺言書情報証明書の交付請求が必要となること、遺言書情報証明書の交付請求には、法定相続情報一覧図、遺言者の出生時からの戸籍等、相続人などの戸籍・住民票等が必要なこと、です。
特別方式の遺言
上記の遺言書を書いている余裕がない場合に認められる方法です。
ただし、上記の方式で遺言をすることができるようになった時から6ヶ月間生存すると、本方式の遺言は無効となります。
・死亡危急時遺言
・伝染病隔離者遺言
・在船者遺言
・船舶遭難者遺言
自筆証書遺言の訂正方法
いったん作成した自筆証書遺言であっても、遺言者は、その遺言書を加除・訂正することができます。
加除・訂正の方法は、「遺言者が、遺言書内の加除・訂正場所を指示し、変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつその場所に押印しなければならない」と定められています。
このように、遺言書の加除・訂正は、厳格な方式が規定されており、この要件を満たさない場合は、加除・訂正が無効となってしまいます。ただし、加除・訂正が無効となった場合であっても、加除・訂正前の文言が確認できる場合は、加除・訂正前の遺言書が有効となります。
遺言書の検認
遺言書(公正証書による遺言以外の場合)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
申立先:
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
必要書類:
申立書、遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本、など
費用:
収入印紙800円分、郵便切手
遺言能力
遺言能力とは、遺言者が遺言事項(遺言の内容)を具体的に決定し、その法律効果を理解・判断するのに必要な能力のことです。
遺言能力が争われた判例
東京地裁平成11年9月16日
遺言者は公正証書遺言を作成。法定相続人は4人。遺言書が作成された当時、遺言者はパーキンソン病により認知症が進行し、遺言能力がなかったとして争った事例。
⇒
公正証書遺言は無効。
遺言者は、入院時において、恒常的に他人と意思疎通をする能力に欠け、日常生活に必要な判断、行動を自力ですることが著しく困難な状況にあり、本件遺言公正証書を作成した時点においては、遺言事項を具体的に決定し、その効果を理解するのに必要な能力、すなわち遺言能力を有していなかったと推認するのが相当である。
仮に遺言者に遺言能力があったとしても、遺言者の意識の状態が相当程度低下していたことは、前記認定のとおりであり、そのような状態で、公正証書作成に近接した時期に遺言者が直接関与して作成されたのもでない遺言内容を公証人が読み聞かせ、遺言者はこれに対して自らは具体的な遺言内容については一言も言葉を発することなく、ハー、とか、ハイ、とかいう単なる返事の言葉を発したにすぎず、遺言者の真意の確認の方法として確実な方法がとられたと評価することはできない。
京都地裁平成13年10月10日
新旧2回の公正証書遺言により遺贈がなされた。旧遺言による受遺者である原告は、新遺言は遺言者の遺言能力を欠く状態でなされたものである等と主張して争った事例。
⇒
原告の請求を棄却。
遺言者は、第2遺言作成当時、痴呆が相当高度に進行していたものの、いまだ、他者とのコミュニケーション能力や、自己の置かれた状況を把握する能力を相程度保持しており、また、第2遺言を作成するように思いたった経緯ないし同機には特に短慮の形跡は窺われず、さらに第2遺言の内容は、比較的単純なものであった上、公証人に対して示した意思も明確なものであったことが認められるのであって、これらの事情を総合勘案すると、遺言者は、第2の遺言作成にあたり、遺言をするのに自由十分な意思能力(遺言能力)を有していたと認めるのが相当である。
名古屋高裁平成14年12月11日
遺言公正証書による遺言は遺言能力のない状態で作成されたと主張して争った事例。
⇒
遺言公正証書は無効。
遺言者には、平成元年頃からおかしな言動が見られるようになり、本件遺言作成時点以前に、感情失禁、記憶障害、見当識障害、人物誤認、被害妄想、脱衣行為等の言動が見られた。したがって、本件遺言書作成当時、痴呆は中等度であったが重度に近いものであって、本件遺言の内容を理解し判断する能力、すなわち遺言能力はなかったものと認めるのが相当である。
当事務所の特徴
1 法律と心理カウンセリングとITの専門家です。
2 業務歴が20年以上ありますので、経験・知識が豊富です。
3 当事務所にて遺言書の保管をします。
4 じっくりと話しを伺い、迅速・丁寧・誠実に対応します。
5 閑静な住宅街にあり、アットホームな雰囲気です。
6 公正証書遺言の作成では、当職が証人となります。当事務所では公証役場へ多数の依頼しており、効率的に公正証書遺言を作成できます。
※行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
※本人のご家族からのご相談も歓迎いたします。
※当事務所は『完全予約制』となっております。
料金・諸費用
遺言書案作成:20,000円~
遺言公正証書作成(時価1億円未満):80,000円+実費+公証人手数料
遺言公正証書作成(時価1億円以上):120,000円~+実費+公証人手数料
遺言書の保管(遺言者が亡くなるまでの期間):10,000円
相談料(15分当り):2,000円
電話相談(15分当り)(※1):2,000円
ネット相談(15分当り)(※1※2):2,000円
メール相談(1回)(※1):2,000円~8,000円
各種対応(15分当り):2,000円
(※1)電話・メール・ネット相談の場合、料金は事前にお支払いください。
(料金を多くお振込みされた場合は、残金を返却いたします)
【お振込み先】三井住友銀行 川崎支店 普通口座5559993 名義人:タカハシヒロシ
(※2)ネット相談はZoomを使用します。
※キャンセル料(キャンセル料は1週間以内にお振込みください)
・ご依頼後のキャンセル
:キャンセル時までに行なった事務作業時間×8千円+実費(+公証人手数料)
・ご予約日の2日前までのキャンセル:0円
・ご予約日の前日のキャンセル:5千円
・ご予約日の当日のキャンセル・無断キャンセル:8千円
※ご予約時間に遅刻された場合
交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。
【リンク集】
日本公証人連合会法務省
日本行政書士会連合会
埼玉県行政書士会
日本弁護士連合会